
おはようございます!
ドイツの天才数学者カール・フリードリヒ・ガウスを知っていますか。
数学だけではなく、天文学や物理学にも多大な功績を残したガウス。
300年間誰も証明することができなかった『フェルマーの最終定理』を描いた本にもガウスの名前が出てきています。
『フェルマーの最終定理』では、ガウス自身はフェルマーの最終定理にそこまで興味を示さなかったので、あまり本書には描かれていませんが、ソフィ・ジェルマンという女性数学者がアドバイスを求めた人物として登場しています。
そして、ナポレオン戦争の際、ソフィ・ジェルマンがガウスの身の安全を確保したことで、ガウスの研究が進み数学が進歩していきました。
そうした、数学者達のストーリーを飽きずに描いたのが『フェルマーの最終定理』です。この本を含めて数学の本を紹介した記事もあるので、もしよければチェックしてみてください。
さて、そんなガウスですが、小学生時代にもその天才性を発揮していました。
今日は、ガウス少年が当時の先生から出された問題とその解法を紹介していきます。
ガウス少年が7歳のときに出された問題
ガウス少年が7歳、日本の小学校では2年生のときのことです。
ある日、先生が授業をしているときに忘れ物があることに気づきました。
まだ幼い子ども達ですから、そのまま教室を離れるのはとても不安です。
そこで、先生は子ども達に絶対できない問題を出し、その間に忘れ物を取りに行こうと考えました。


はーい。
1+2=3 3+3=6 6+4=10・・・。
そして、その問題を子ども達に出題して、教室を出ようとしたとき、ガウス少年が言いました。
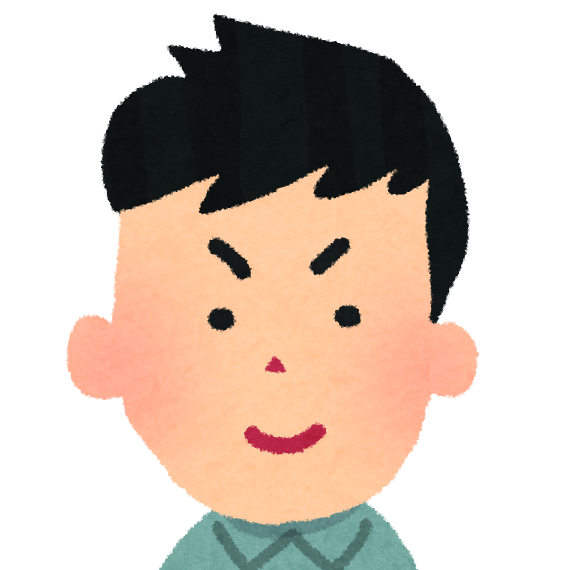

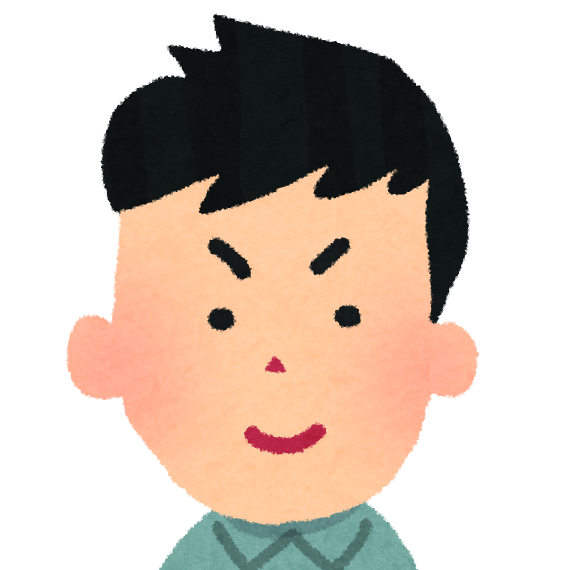
なんと、問題を出して先生が教室を出る前に、ガウス少年は答えを言い当てました。
先生も他の子ども達も信じられないような目でガウス少年を見ました。

ガウス少年の解法 1から100までの総和
ガウス少年はどのようにして【1から100までの和】を計算したのでしょうか。
問題自体は7歳の子にも理解できる足し算の問題です。
しかし、数学を学んでいる人ならお気づきの通り、これは高校生で習う等差数列の和の問題です。
等差数列とは、隣接する各項の差が等しい数列である。隣接する項の差を公差という。例えば、5, 7, 9, … は初項 5, 公差 2 の等差数列である。同様に、1, 7, 13, … は公差 6 の等差数列である。
日本では高校生で習うような公式を7歳の子が独自に発見したことになります。
では、実際にはどのようにして解いたのでしょうか。

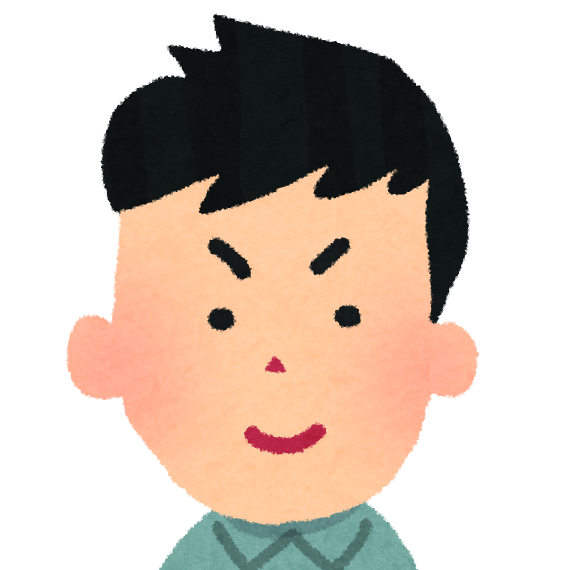
$$ 1+2+3+4+5+・・・+95+96+97+98+99+100 $$
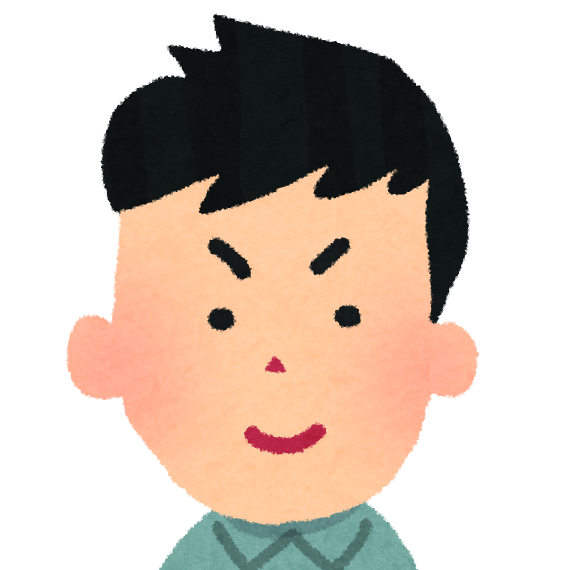
$$ 1+100=101 2+99=101 3+98=101 4+97=101 5+96=101 ・・・ $$
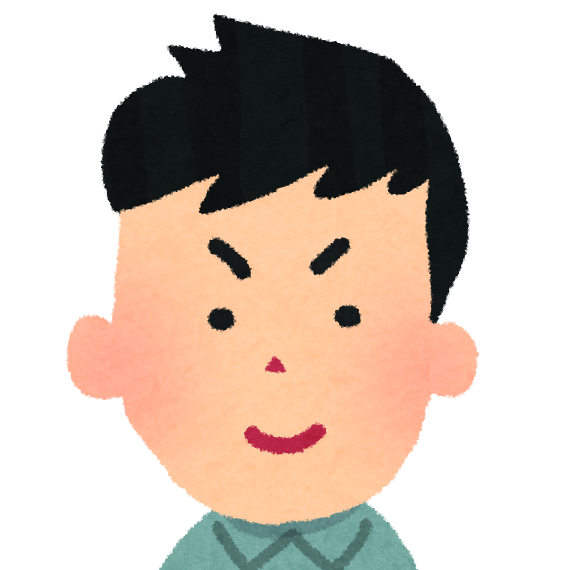
すると、すべての計算結果が101となります。
先生、この101はいくつできるかわかりますよね?

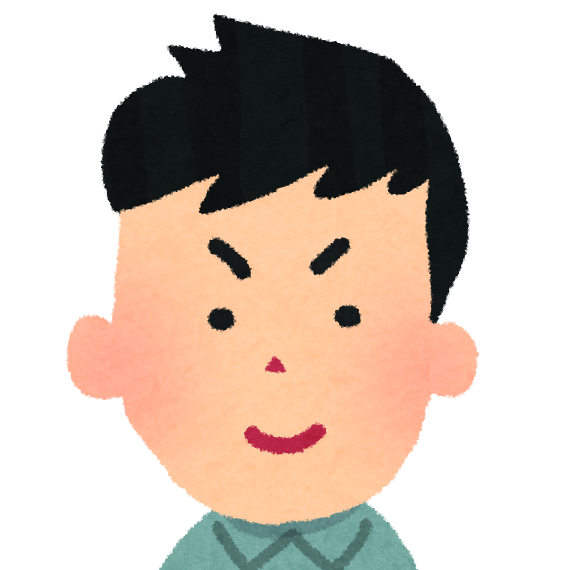
その通りです。
ですから、101が50個あるということは、かけ算すれば答えが導かれますね。
$$ 101×50=5050 $$

実際にはこのようなやりとりがあったかは知りませんが、1から100までの和の解法は上のようになります。
1から100までだとなぜ101が半分の50個になるかがわかりずらい人は、1から10までで考え直してみるとわかりやすくなります。
1から10までの和
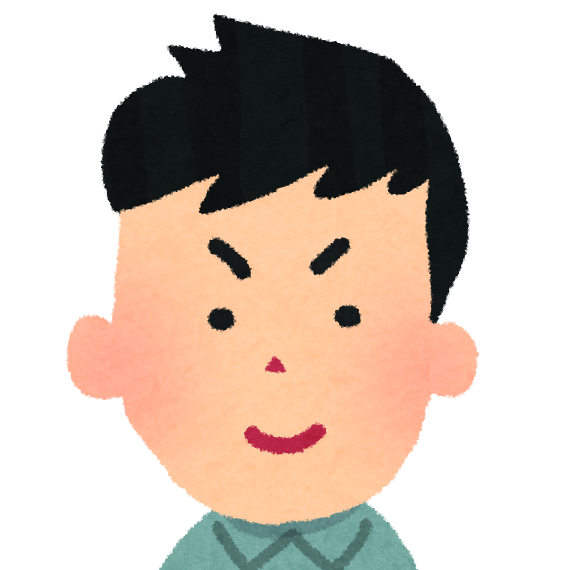
1から10までの和は、順にたし算してもわかりますよね。
答えは55になります。
$$ 1+2=3 3+3=6 6+4=10 10+5=15 $$
$$ 15+6=21 21+7=28 28+8=36 36+9=45 45+10=55 $$
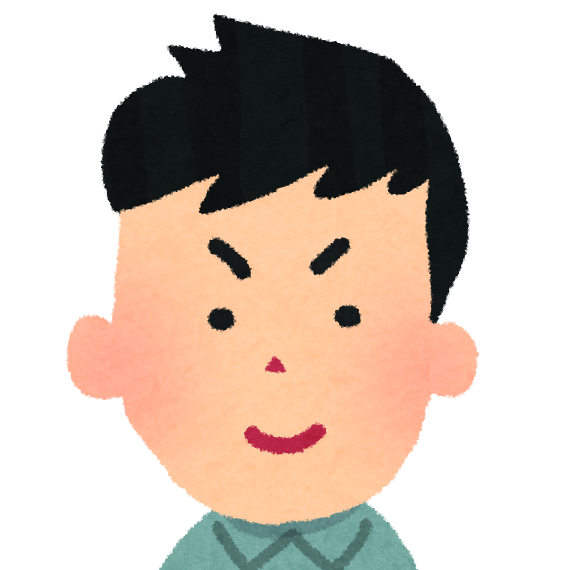
では、これを1から100までの和での解法のように解いていきます。
まずは、両端同士を順にたし算していきます。
$$ 1+10=11 2+9=11 3+8=11 4+7=11 5+6=11 $$
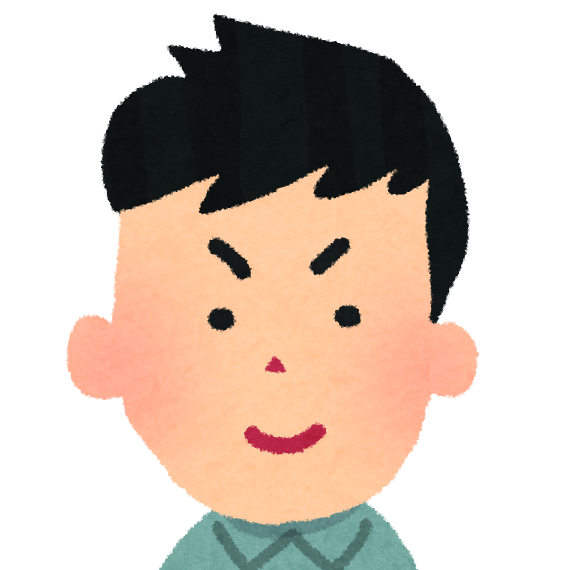
すると、「11」が「5つ」できましたね。
このとき、「11」は全てのたし算の結果。
一方、「5」は今回使われた数(1〜10)の半分の個数になっていますよね。
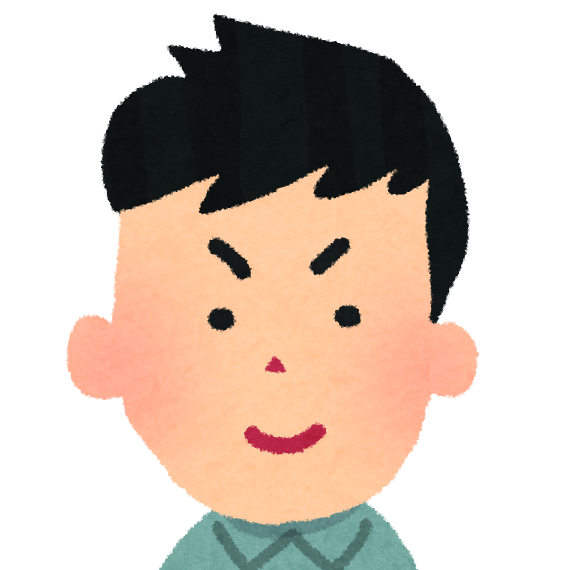
$$ (1+10)×(10÷2) =11×5=55 $$
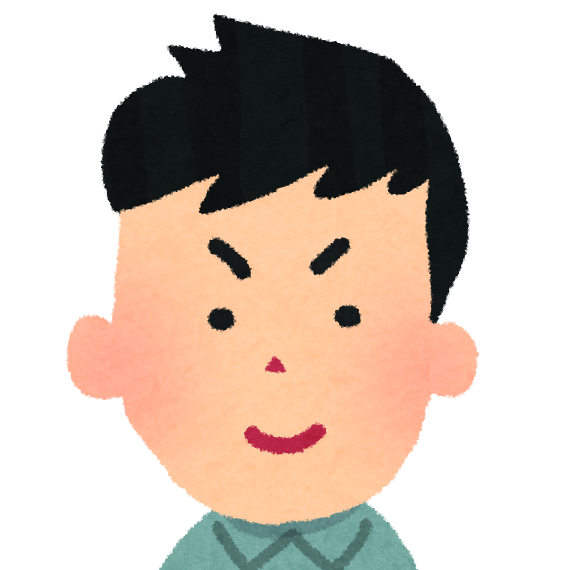
最後に 数学者の逸話はとても魅力的!!
以上ガウスの逸話をもとに、1から100までの和の解法を紹介しました。
天才と呼ばれる数学者が、どのような人生を歩んでいるかを知ることはとても面白いです。
エピソードひとつひとつが凡人にはない考えなので、それを知るだけでも「なるほど!!」と嬉しくなります。
過去の数学者の逸話や功績はストーリーとしてとても魅力的です。
今の数学ができあがるまでに、どれほどの天才達が知識を積み上げてきたかを知るだけでも人生にとってプラスになると思います。
特に上でも紹介しましたが、『フェルマーの最終定理』はおすすめです。
この一冊で紀元前から現代までの有名な数学者について知ることができます。
数学が苦手な方でも、読み物としても優秀なのでスラスラ読むことができます。
気になる方はチェックしてみてください!













